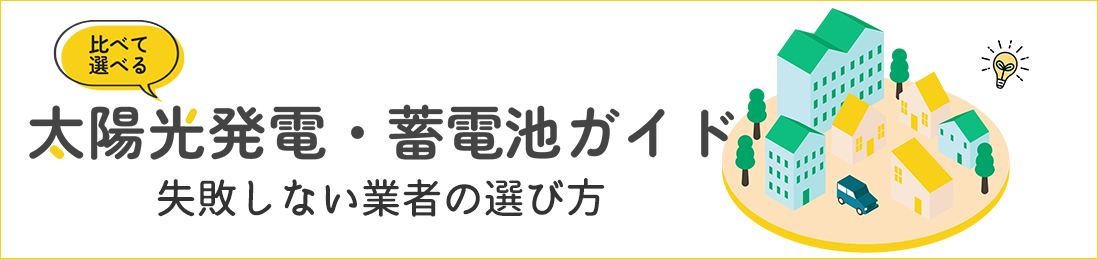太陽光発電の固定価格買取制度と新たな電力活用法とは

固定価格買取制度(FIT制度)は、太陽光発電の導入を促進するための重要な仕組みとして、発電事業者に安定した収益を提供しています。しかし、FIT制度の終了後には新たな電力活用法が求められています。EV、蓄電池、V2Hといった技術の活用により、余剰電力を効率よく自家消費し、持続可能なエネルギー供給を実現する方法が注目されています。
目次
固定価格買取制度が未来の電力を支える
固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーで発電された電力を電力会社が一定価格で買い取る仕組みです。これにより、発電事業者は安定した収益を見込め、設備投資のハードルも下がります。
◇固定価格買取制度とは
固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーの普及を促進するための仕組みとして、2012年に日本で導入されました。この制度では、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーで発電された電力を、一定の価格で一定期間、電力会社が買い取ることが保証されています。
この仕組みは、発電事業者が設備投資を行いやすくし、収益の見通しを立てやすくする目的で設計されました。具体的には、2024年度に10kW以下の太陽光発電システムを導入した場合、10年間にわたり1kWhあたり16円での買い取りが保証されます。
この固定価格により、発電事業者は市場価格の変動に左右されることなく収益を確保でき、個人や企業が再生可能エネルギーの導入に踏み切るハードルを下げる効果を発揮しています。
◇FIT制度誕生の背景
固定価格買取制度(FIT制度)が誕生した背景には、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上という課題がありました。特に、日本はエネルギー資源の大半を輸入に依存しており、これが経済的にも地政学的にも大きなリスクとなっています。
この状況を改善するため、国内で利用可能な再生可能エネルギーの活用が重要視されるようになり、東日本大震災による原子力発電の縮小もFIT制度導入の後押しとなりました。震災後、エネルギー政策の見直しが求められる中、持続可能で安全性の高い再生可能エネルギーの導入が急務とされました。
しかし、再生可能エネルギーの普及には高額な設備費用が障壁となっていました。FIT制度は、この初期費用負担を軽減し、導入後の収益見通しを安定させる仕組みとして設計されました。また、FIT制度には再生可能エネルギーの普及に伴う経済効果も期待されています。
発電事業の拡大が、新たな雇用創出や地方経済の活性化にもつながると考えられています。このように、FIT制度はエネルギー政策の転換点として、持続可能な未来を築くための重要な役割を果たしています。
固定価格買取制度における初期費用や収益減少の課題

画像出典:フォトAC
固定価格買取制度(FIT制度)においては、初期費用や収益減少といった課題が重要な検討ポイントとなります。この制度は再生可能エネルギーの普及を促進するために導入されましたが、その導入を考える際には、設備のコスト負担や長期的な収益の見通しについての理解が不可欠です。
◇初期費用がかかる
太陽光発電の導入において、最も大きな課題の一つは初期費用の高さです。例えば、一般住宅用の10kW未満の太陽光発電システムを設置する場合、平均で約27万円/kW(2023年度)もの費用がかかります。この金額には、ソーラーパネルやパワーコンディショナーなどの設備費用に加え、工事費用も含まれています。
さらに、蓄電池を併せて導入する場合は、その分の追加費用も必要となり、総額がさらに増大します。加えて、導入後の売電収入や電気料金の削減額を考慮しても、初期投資を回収するまでに数年を要するケースが多いです。
◇メンテナンスの問題
太陽光発電システムは、設置後も定期的なメンテナンスが欠かせません。特に、屋外に設置されるソーラーパネルは、雨風や雪の影響を受けやすく、汚れや損傷が発電効率の低下につながります。
例えば、茨城県など降雪が少ない地域でも、花粉や砂埃による汚れが原因で発電量が減少する事例があります。また、台風や強風が頻繁に発生する地域では、自然災害によるパネルの破損が懸念されます。
これらのリスクを軽減するためには、専門業者による定期点検や必要に応じた修理が必要ですが、これらのメンテナンス費用もランニングコストとして計算に入れる必要があります。こうした課題は、FIT制度を利用して導入する際に見落とされがちなポイントです。
◇卒FITで収益が減る
FIT制度の適用期間が終了する「卒FIT」を迎えると、電力の買い取り価格が大幅に下がる点も重要な課題です。例えば、FIT制度適用中の2024年度における10kW未満の買い取り価格は1kWhあたり16円ですが、卒FIT後の買取価格は8円前後まで減少することが一般的です。これは収益性の低下を意味し、初期投資の回収期間が延びる可能性を示唆しています。
また、新しい電力事業者を選ぶ場合、買取価格の条件は事業者ごとに異なります。そのため、卒FIT後も収益を最大化するためには、地域の電力市場や買取事業者の条件を比較検討することが不可欠です。こうした対応ができない場合、導入時の収益計画が崩れる可能性があるため、注意が必要です。
再生可能エネルギーで地球温暖化防止
化石燃料に依存する従来のエネルギーシステムは、二酸化炭素の排出を増加させ、地球の気候変動を加速させる一因となっています。再生可能エネルギーは、その持続可能性と環境負荷の少なさから、地球温暖化防止に向けた効果的な解決策として期待されています。
◇発電コストの低下
再生可能エネルギーの普及が進む中、発電コストの低下が大きなメリットとして注目されています。特に、太陽光発電は固定価格買取制度(FIT)の導入以降、設備の大量生産や技術革新が進み、コスト削減が実現しています。
例えば、2021年に経済産業省が発表した試算では、2030年には太陽光発電のコストが原子力発電よりも低くなると予測されました。この動きにより、再生可能エネルギーは「高コスト」というイメージが薄れつつあります。
さらに、栃木県や茨城県、群馬県といった地域では、住宅の屋根を活用した小規模な太陽光発電の導入が増加しています。このような地域単位の取り組みが、市場の拡大を後押しし、設備費用や設置コストのさらなる削減につながっています。
加えて、発電コストが下がれば、電力料金の低下も期待でき、家庭や事業者の電気代負担が軽減されるのです。これにより、再生可能エネルギーの導入が進むと同時に、電力供給の安定性も向上します。
◇環境と経済を両立
再生可能エネルギーは、環境保護と経済成長を両立させる手段として期待されています。例えば、日本はエネルギー自給率が2020年時点で11.3%と低く、国際的に見ても課題が大きい国です。
しかし、太陽光発電や風力発電を中心とした再生可能エネルギーの導入により、エネルギー自給率を引き上げ、輸入燃料への依存度を低減することが可能です。これにより、エネルギーの安定供給が確保され、経済的な安定性も向上します。
さらに、再生可能エネルギーは地球温暖化の抑止にも寄与します。農業が盛んな地域では、太陽光発電を導入することで、農地の活用効率を高めながら二酸化炭素の排出削減を実現する取り組みが進められています。
このような取り組みは、地域経済の活性化と環境保全を両立させる好例です。また、再生可能エネルギーへの投資は、新たな雇用を生み出す効果も期待されています。
EV・蓄電池・V2Hを活用!卒FIT後の電力自給
EV(電気自動車)や蓄電池、V2H(Vehicle to Home)等の技術を組み合わせることで、太陽光発電で得た余剰電力を自家消費し、家庭内での電力自給を可能にします。
◇自家消費をする
卒FIT後に最も重要となるのが、余剰電力を自家消費するための仕組みを整えることです。まず、太陽光発電で得られた電力を効率よく利用するためには、蓄電池の設置が鍵となります。
これにより、昼間に発電した電力を夜間や天候の悪い日にも使用でき、自家消費が促進されます。電力の購入を最小限に抑え、電気代を削減することが可能になるのです。また、EVやPHEVの導入も有効です。
これらの車両は、太陽光発電の余剰電力を充電に利用でき、家庭での消費電力を補う役割を果たします。例えば、昼間に発電した電力で車を充電し、夜間の家庭内消費分を補うといった活用法が一般的です。多くの地域でEVの導入が進んでおり、自家消費を促進する取り組みが進んでいます。
◇V2Hの導入
さらに進んだ電力自給の方法として注目されているのが、V2H(Vehicle to Home)の導入です。V2Hは、EVやPHEVに蓄えられた電力を家庭で利用する仕組みで、災害時の非常用電源としても利用できます。
V2H対応の充電器を導入することで、車と家庭の電力を双方向にやり取りでき、昼間に発電した電力を車に充電し、その電力を夜間に家庭で利用するといった柔軟な運用が可能になります。
例えば、EVとV2Hを組み合わせたエネルギー自給モデルが注目され、自家消費率を高め、地域のエネルギー自立を進める取り組みが進行中です。さらに、災害時には車両の電力を非常用電源として活用することができるため、ライフラインの維持にも貢献します。
加えて、昼間の余剰電力を車に充電し、ピーク時の高い電力料金を避けるといった賢い運用も可能です。これにより、卒FIT後の家庭にとって電力負担を軽減することができます。
固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーの普及を促進するため、日本で導入された仕組みであり、安定した収益を得られる仕組みです。FIT制度の導入により、発電事業者は設備投資のハードルを下げ、収益の見通しを立てやすくしています。
地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上が背景にあり、FIT制度は再生可能エネルギーの導入を後押しし、エネルギー自給率を高める一方で、卒FIT後の課題として収益減少や電力の自家消費が重要視されています。 EV、蓄電池、V2Hの導入により、余剰電力を家庭で利用し、自家消費を促進する取り組みが進められ、持続可能なエネルギー供給を実現しています。